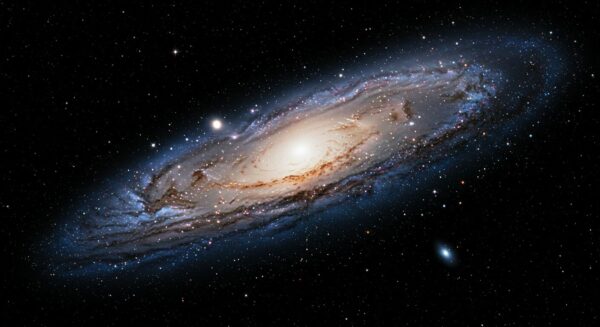また変な投稿を失礼します。
010コーヒーでは「万物は全部波動、周波数じゃん」という仮定の下、「周波数が人に与える影響」と「音楽」、そして「コーヒー」を融合させて何か素敵なことができないかを模索しております。
すでに先駆者、先達がいらっしゃるので、その方々について調べてみました。
これは私の思考整理のためのメモなので、ご興味のない方はブラウザバック推奨ですが、もし「おや?変な記事だな」と思ってくれた方は同志ですので、ちょっと寄っていってください。
【注意】本記事は専門的に研究された方々の発言や記事を引用させていただきますが、それらをあくまでも素人の010コーヒーがまとめ、意見をいたします。よって記事の内容は眉唾であり、資料的価値は皆無であることをここに明記しておきます。くれぐれもご容赦ください。
古川茂人教授
静岡社会健康医学大学院大学にて教鞭をとっておられる先達その1。AIに質問したら真っ先にお名前がでてきました。「聴覚情景分析のメカニズム」について研究されていらっしゃる。
聴覚を中心とした認知神経科学(心理物理学・神経生理学)の研究に従事しています。特に聴覚情景分析のメカニズム(脳が複雑な音環境を把握するための仕組みや手がかり)、生理機能の計測・評価・モデリング、「聞こえ」の困難のメカニズムと評価に興味を持ち、研究してきました。
https://researchmap.jp/shig より引用
(010が考える)聴覚情景分析
人間って、鼓膜で受け取った音の波を、結構随意に選り分けて聞くことができるのは不思議だなーと思っていたので、教授の研究を読ませていただくの楽しそう。
- ものすごいうるさい雑踏から、「これはサイレンの音」とか「あれは友達の声」とか聴き分けられる
- 上空を頻繁に飛ぶ飛行機の爆音にビビっていたけど、数か月で全然気にならなくなった。(なんなら意識しないと聞こえなくなった)
- 田舎に住んでいた時、最初はカエルの大合唱で夜眠れん!とか思っていたけど、そんなの1週間で慣れたこと
自分の経験だけでもこんだけあるなぁ。
その他、NTTコミュニケーション科学基礎研究所でも人間情報研究部 上席特別研究員として名を連ねていらっしゃる。そこのサイトにリンクのある「錯視と錯聴を体験」できるサイトが面白かった!知覚的補完のページとか、改めて聞くとめちゃ気持ち悪い(;^ω^)けど、聞くほど「人間の聴覚とかってすげぇ!」となるので、一度聞いてみてごらんなさい。
代表的な論文:
- 「Neural correlates of auditory perception in the human brain」
- 「Time-domain analysis of the brain’s response to complex acoustic stimuli」
- 「音響刺激による脳波誘導と認知機能の関連性」
粂田昌宏先生
粂田昌宏先生は電磁波や振動刺激の生体影響を研究されているそう。特に気になったのは、「可聴域音波に対する細胞応答の探索」という研究テーマ。
音(可聴域音波)は、我々動物個体にとって、外界認識やコミュニケーションのツールとして非常に重要な役割を果たしますが、細胞レベルでは影響を及ぼし得るかどうか、これまでほとんど科学的研究がなされてきませんでした。我々はこの点に着目し、細胞が音に対して何らかの応答を示すかどうかを探索し始めました。これまでのところ、音波暴露依存的に抑制される遺伝子群を見出すとともに、音圧や波形がこの抑制効果に重要な要素であること、細胞種によってこの遺伝子応答の度合いが大きく異なること、などを明らかにしました。
https://www.chrom.lif.kyoto-u.ac.jp/member/3.html より引用
音が細胞に与える影響とかまさに010コーヒーが気になっているテーマそのもの。「音波暴露依存的に抑制される」というのは、「音に曝された方が良くて、それで不活性化する遺伝子がある」ってこと?用語が難しくて凡人010コーヒーには理解が及ばない…
しかし、先生のご発言で「~実は細胞レベルで音を認識するシステムが存在するのかもしれません。」というのは見逃せません。ピュアオーディオ勢の肩を持つわけではありませんが、人間は耳だけで音を聞いているわけではないのは010コーヒーも痛感しているところですので、もっと知りたいところ。
代表的な論文:
- 「非侵襲的電磁波刺激による脳機能の修飾効果」
- 「Modulation of cognitive functions using vibrational stimuli」
- 「周波数特性の異なる刺激が自律神経系に与える影響の解析」
ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ(Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz)氏
ヘルマン・フォン・ヘルムホルツは、19世紀のドイツの科学者であり、物理学、生理学、心理学など幅広い分野で業績を上げた人物。音や振動に関する功績もその一つです。
全部書くとものすごい文字数になりそうなので、音に絞って。
音響学
- 音の共鳴現象の解明:
- 彼は、音の共鳴現象を実験と理論によって詳細に研究しました。
- 特に、ヘルムホルツ共鳴器(なんか水滴みたいな形の金属)と呼ばれる装置を用いて、様々な音の周波数を分析し、共鳴現象のメカニズムを明らかにしました。
- ヘルムホルツ共鳴器は、現在でも音響学の分野で広く用いられています。

固有振動数もものすごい興味ある。なんでほとんどの物質が固有の振動を持っているのか?石とか金属とか、一見振動しなさそうなものなのに…
- 音色理論の提唱:
- 彼は、音色(音の聴こえ方)が、音に含まれる様々な周波数の成分(倍音)によって決まるという理論を提唱しました。
- この理論は、音楽や音声の分析に重要な役割を果たしました。
- 聴覚の研究:
- 彼は、聴覚のメカニズムについても研究を行い、蝸牛(内耳にある器官)の構造と機能が音の聴こえ方にどのように影響するかを明らかにしました。
ジェームズ・ギンブル(James Gimzewski)教授
カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の教授で、細胞から発せられる音波(ナノメカニカル振動)に関して研究。「ソノサイトロジー(sonocytology)」と呼ばれる分野の創始者で、細胞が発する超音波振動を検出し、健康な細胞とがん細胞の違いや、細胞の状態変化を研究しています。
「The Rhythmic Sound of Living Cells」という記事は、そのタイトルからして非常に興味深い。
レコードにおける「針」のような仕組みで、「細胞の音」を聴くための『原子間力顕微鏡(AFM)』というインターフェースで、人間の可聴域まで増幅する方法をとっているようです。
将来、医療診断や治療に大きな可能性を秘めている、非常に面白そうな研究です。ただ、「sonocytology」で検索しても、最新の記事が2020年なので、研究が止まっていないか心配だ。
The ‘song’ of a living cell made visible
The Dark Side of the Cell
リチャード・デイビッドソン(Richard Davidson)氏
ウィスコンシン大学マディソン校の神経科学者で、音波や振動が脳波パターンに与える影響について研究。
特に瞑想中の脳波変化や、特定の周波数の音が脳の状態に与える影響を調査し、精神的健康との関連を探っています。「感情の神経科学」の分野で著名な研究者。
「可塑性」というと、どうしてもメタルギアに出てきたC4爆弾のオタコンの説明が思い出されるが、「脳の可塑性」というと、脳が状況や外部刺激に応じて変質することのようだ。
また、氏はダライ・ラマ14世とも交流があり、「瞑想」と「脳」との関連についてもコミュニケーションをとりながら研究しているそう。
二コラテスラ氏の動画
サッカーフィールドが例に出てくるあたり、誠に良い。
まとめ
今回、これまで漠然としたイメージだったものを、AIの力も借りながら、自分なりに一歩踏み出してみた。
まずは先達の通った跡を、と思って、各界の研究者たちを調べてみたが、やはり面白い!まだまだ未開拓な分野であり、科学が進んだ今こそ、原点回帰、人間にフォーカスしても良いんじゃないか?と感じた。
次回は「脳と聴覚」「音楽や音が脳に与える影響」について調べてみたい。
美味しいブレンド販売中!
まだまだテーマを具現化するようなブレンドはできていませんが、それでも私の10年の経験をフルに落とし込んだ「010ブレンド」は最高に美味しいです!ぜひ思索のお供にどうぞ。

#マイクロコスモス #波動 #精神 #哲学